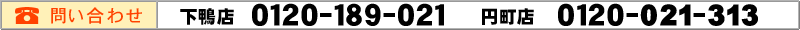京都市左京区松ヶ崎の不動産をご紹介します。
新築一戸建・中古住宅・中古マンション・売土地を掲載しております。
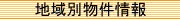 小学校区を基準に地域分けした
小学校区を基準に地域分けした不動産情報をご紹介します
- ご予算で検索
- 地域・学区から検索
- 特選物件
- 条件登録
- 21コンシェルジュ
- 会員登録
- 購入の基礎知識
- 物件資料の見方
- 新築住宅施工例
- オープンハウス
- 室内見学ムービー
- 新聞広告集
- ローンシミュレーション

[学区] 松ヶ崎小学校区
[地域] 京都市左京区松ヶ崎
左京区でも人気の優良住宅地である「松ヶ崎」の不動産特集ページです。
この学区で新しく売り物件が出たらメールを受ける京都市左京区 松ヶ崎の新築戸建
京都市左京区松ヶ崎の地域紹介
地名の由来
松ヶ崎の地名は、この地の丘陵地帯が北山の出崎で、松樹の茂ることに由来すると言われます。 『京都大事典』より松ヶ崎の地図
松ヶ崎の範囲を赤線で囲ってあります。地域内の北半分は山地です。緑の多い・近い地域です。
クリックで拡大 約600kb gif形式
松ヶ崎のお店
北山通には多くの結婚式場、二次会に使えそうなレストランが建ち並び華やかです。北大路通にはコープ下鴨、高野川をわたればカナート洛北やイズミヤ高野店があり便利です。スーパーは下鴨本通りのフレンドフーズや、修学院駅前にも数件あります。※施設・店舗などは平成23年10月現在のものです。詳しくはスタッフまでお尋ね下さい。
松ヶ崎の施設
中央には左京区新総合庁舎・京都工芸繊維大学・ノートルダム女子大学などがあります。南側には松ヶ崎浄水場、北側には宝ヶ池球技場もあります。※施設・店舗などは平成23年10月現在のものです。詳しくはスタッフまでお尋ね下さい。
松ヶ崎の自然
南側を流れる疎水分流は春は桜並木、初夏は蛍、夏は涼しい木陰となり、東から西へ向けていつもゆったり流れています。また、北側にある山地には、五山の送り火の「妙・法」や、多くの寺社仏閣、ジョギング・ウォーキングの人気コースの宝ヶ池公園などもあります。
松ヶ崎の歴史
深泥池周辺はいくつもの遺跡が見つかっていることから、古代から人の住んでいた地域とされています。送り火「妙」で有名な西山の頂上では、松ヶ崎西山群集墳が見つかっています。松ヶ崎の村の始まりは、平安遷都(794年)の際に、奈良平城京で農事に巧みな者100人を選んで、皇室向けの米作り専用として、集団移住させた事による、といわれています。
お百姓たちは各世帯に田一町(3000坪)と山一枚を与えられました。このため、松ヶ崎では分家が認められなかったので、500年間ほどの間ほとんど人口の増加がなかったそうです。
この百世帯は今は立正会という会を作り、涌泉寺の題目踊り、妙法の送り火などを守っています。
今の北山通の北側の道が旧道にあたり、旧道沿いに集落が広がっていてました。大正の初め頃までは、その南は広く田が広がっており、「条里制」という方法で区分されていました。
現存する「六ノ坪町」という町名からそういった当時の様子がうかがえます。
松ヶ崎の受難の歴史は、水田の水をめぐる周辺の村との争い、全村法華宗改宗を受けた比叡山からの弾圧(鎌倉時代)、寛正の飢饉(室町時代)と土一揆への弾圧など、多く記録が残っています。
江戸時代中期には水不足や干ばつへの対策として、深田をため池として改造し、今の宝ヶ池ができました。
その後明治初期には松ヶ崎小学校、大正に入り松ヶ崎浄水場、松ヶ崎保育園、アメリカ人宣教師が開いた聖光幼稚園などができました。
昭和初期には京都高等工芸学校(現在の工芸繊維大学)もでき、教育施設の多い地域となります。
昭和6年に京都市に編入。分家を禁じるしきたりのためそれまでほとんど変わらなかった人口も、この頃より増え始めます。昭和6年で約1000人、平成の始めでは約7000人となります。
昭和39年には国立京都国際会館が完成、宝ヶ池競輪場跡に市営子どもの楽園ができ、昭和40年には宝ヶ池トンネルが完成し、松ヶ崎と岩倉が近くなりました。
平成に入り北山通りの完成、地下鉄の延長と松ヶ崎駅の開設につながり、今日に至っています。
『松ヶ崎』(松ヶ崎立正会)より
更新日時:
2026/02/15 17:47

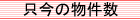
公開物件数 :535
(松ヶ崎の公開物件数 : 6 )
会員物件数 :764
(松ヶ崎の会員物件数 : 10 )
全物件数 :1299
(松ヶ崎の全物件数 : 16 )
 会員登録はこちらからどうぞ
会員登録はこちらからどうぞ
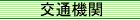
地下鉄烏丸線
「北山駅」・「松ヶ崎駅」
叡山電鉄「修学院駅」
市バス
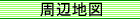 京都市左京区松ヶ崎の地図
京都市左京区松ヶ崎の地図
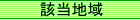
このページの物件がある町名
松ヶ崎泉川町
松ヶ崎壱町田町
松ヶ崎井手ケ海道町
松ヶ崎井手ケ鼻町
松ヶ崎今海道町
松ヶ崎榎実ケ芝
松ヶ崎大谷
松ヶ崎海尻町
松ヶ崎河原田町
松ヶ崎北裏町
松ヶ崎狐坂
松ヶ崎木鐙籠町
松ヶ崎木ノ本町
松ヶ崎境ケ谷
松ヶ崎久土町
松ヶ崎雲路町
松ヶ崎鞍馬田町
松ヶ崎小竹藪町
松ヶ崎小脇町
松ヶ崎御所海道町
松ヶ崎御所ノ内町
松ヶ崎桜木町
松ヶ崎笹ケ谷
松ヶ崎三反長町
松ヶ崎芝本町
松ヶ崎修理式町
松ヶ崎正田町
松ヶ崎城山
松ヶ崎丈ケ谷
松ヶ崎丈ケ谷町
松ヶ崎杉ケ海道町
松ヶ崎千石岩
松ヶ崎総作町
松ヶ崎高山
松ヶ崎糺田町
松ヶ崎堂ノ上町
松ヶ崎中海道町
松ヶ崎中町
松ヶ崎西池ノ内町
松ヶ崎西桜木町
松ヶ崎西町
松ヶ崎西山
松ヶ崎寝子ケ山
松ヶ崎橋上町
松ヶ崎林山
松ヶ崎東池ノ内町
松ヶ崎東桜町
松ヶ崎東町
松ヶ崎東山
松ヶ崎樋ノ上町
松ヶ崎平田町
松ヶ崎堀町
松ヶ崎丸子
松ヶ崎深泥池端
松ヶ崎南池ノ内町
松ヶ崎村ケ内町
松ヶ崎柳井田町
松ヶ崎横縄手町
松ヶ崎呼返町
松ヶ崎六ノ坪町

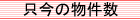
公開物件数 :535
(松ヶ崎の公開物件数 : 6 )
会員物件数 :764
(松ヶ崎の会員物件数 : 10 )
全物件数 :1299
(松ヶ崎の全物件数 : 16 )
会員ページログイン
地下鉄烏丸線
「北山駅」・「松ヶ崎駅」
叡山電鉄「修学院駅」
市バス
このページの物件がある町名
松ヶ崎泉川町
松ヶ崎壱町田町
松ヶ崎井手ケ海道町
松ヶ崎井手ケ鼻町
松ヶ崎今海道町
松ヶ崎榎実ケ芝
松ヶ崎大谷
松ヶ崎海尻町
松ヶ崎河原田町
松ヶ崎北裏町
松ヶ崎狐坂
松ヶ崎木鐙籠町
松ヶ崎木ノ本町
松ヶ崎境ケ谷
松ヶ崎久土町
松ヶ崎雲路町
松ヶ崎鞍馬田町
松ヶ崎小竹藪町
松ヶ崎小脇町
松ヶ崎御所海道町
松ヶ崎御所ノ内町
松ヶ崎桜木町
松ヶ崎笹ケ谷
松ヶ崎三反長町
松ヶ崎芝本町
松ヶ崎修理式町
松ヶ崎正田町
松ヶ崎城山
松ヶ崎丈ケ谷
松ヶ崎丈ケ谷町
松ヶ崎杉ケ海道町
松ヶ崎千石岩
松ヶ崎総作町
松ヶ崎高山
松ヶ崎糺田町
松ヶ崎堂ノ上町
松ヶ崎中海道町
松ヶ崎中町
松ヶ崎西池ノ内町
松ヶ崎西桜木町
松ヶ崎西町
松ヶ崎西山
松ヶ崎寝子ケ山
松ヶ崎橋上町
松ヶ崎林山
松ヶ崎東池ノ内町
松ヶ崎東桜町
松ヶ崎東町
松ヶ崎東山
松ヶ崎樋ノ上町
松ヶ崎平田町
松ヶ崎堀町
松ヶ崎丸子
松ヶ崎深泥池端
松ヶ崎南池ノ内町
松ヶ崎村ケ内町
松ヶ崎柳井田町
松ヶ崎横縄手町
松ヶ崎呼返町
松ヶ崎六ノ坪町